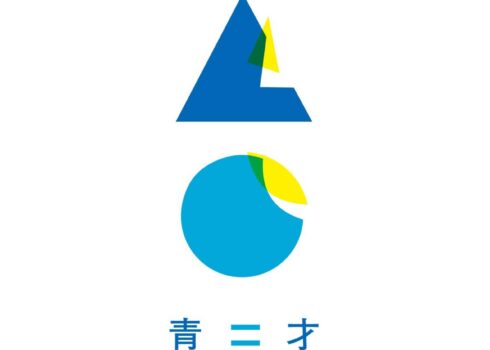- とちぎのしゅし
- 脇雅昭(よんなな会・主催)後半|tochigi gene


脇雅昭(よんなな会・主催)後半|tochigi gene

―後半―
――――――――――――――
若者の人生の選択肢を増やしたい。
脇さんの「やりたい事」を教えてください。
学生の可能性
総務省の採用担当をやらせて頂いている時に、「応募者の想いが伝わってこないなぁ」と思う事が多かったんです。最初は「もっと自分出せよ」と言っていましたが、ある時、その就職活動自体の「構造」に疑問が湧きました。
学生にとっての就職活動って、なんとなく社会から、「就職しなければいけない」という状況に置かれがち。そのプレッシャーで「決めなくちゃ」みたいな状況になり「志望動機」をひねり出しながら一所懸命に話してくれているのかと。さらに、そこで出会う大人が「採用権限をもっている人」なわけです。
その立場で「自分出せよ」と言うのは、私のエゴだなと感じました。そこから「じゃあどうやったら、自分と学生がフラットな関係になれるか」と考え始めたんです。
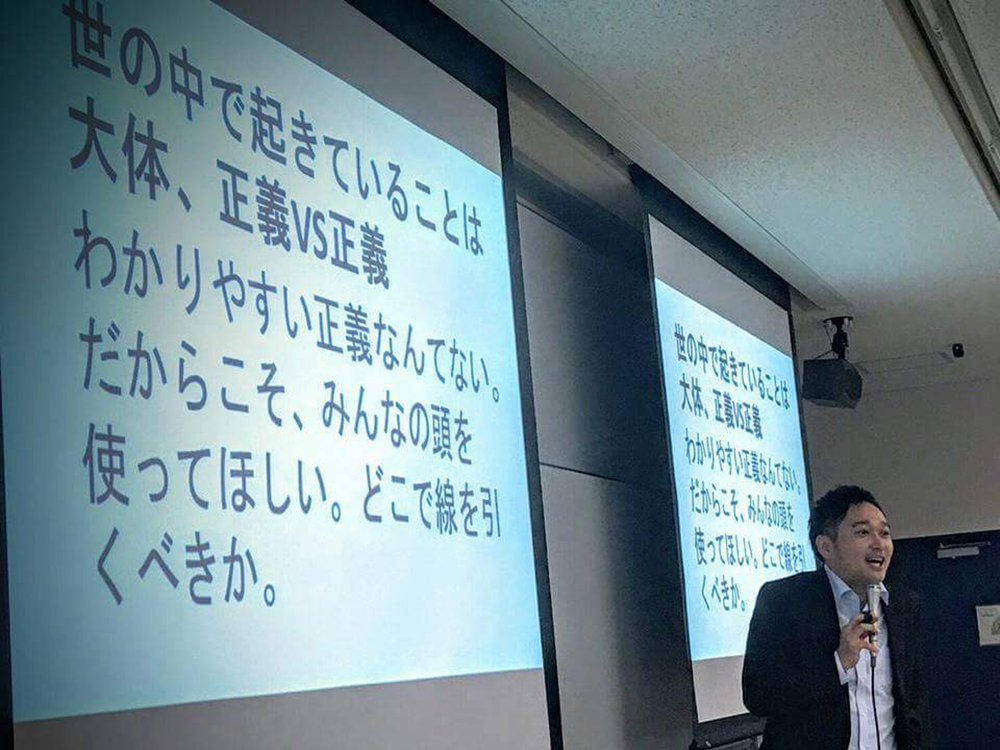
結論は、多くの学生が、具体的な「想い」や「結果」を持っている「大人」と「接点」を増やす事。
そして、選択肢を知り、その中から選んでもらえれば、「想い」も具体的になるんじゃないかと。
→学生全体の活性を見た素晴らしい視点ですね。
私も人事統括として新卒の採用をしていた際には「ご縁があっても、無くても日本を一緒に良くしていきましょう」と言うようにしていました。
「採用の有無に関わらず、その人が自分をキャッチして活躍して欲しい」という発想ですね。面接では「合う合わないは事実あるから、出来る限りありのままの自分の言葉で」という前提を定義。選考の視点と共に、学生への付加価値として「思考をブラッシュアップする機会」という視点を持っていました。マッチングの度合いは就業した後も重要ですしね。
誰と出会うか
学生を見ていて感じるのは、起業する学生は、親や周りで同じように起業している人がいるんです。「こういう選択肢があるんだ」って勝手に背中を見ている。逆に、抽象的な選択肢の中からでは抽象的な選択しかできないんじゃないか、と思いました。
→すっごくわかります。環境においての情報格差は存在していて、「選択肢、考え方、心理面」など多岐に影響している点は私も課題視しています。
言い訳はできないように、「地元が一緒で、活躍してる人」に会ってもらう。それなら学生も「俺も頑張ろう」ってなれる。先輩社会人にとっても、地元の後輩に対する思い入れは強いだろうと考えました。
これがすごくいい会になったんです。ほんと「出会い」や「環境」は重要だなと再実感しました。

「やりたい!」の力
国という観点から考えると、少子高齢化で確実に日本人は少なくなります。国の発展を目指す場合、これからは一人一人がパフォーマンスを上げていく事が重要です。
「想い」という視点でいえば「やらなければならない」と思っている状態と「やりたい」という状態では全然パフォーマンスが違うと考えています。自分の中の「やりたい」を見い出し、自分で選択してやっていく事がいいのではないか。その「やりたい」が、色々な大人と会う中で形をなしていくんじゃないかって思うんですよね。
→鋭いですね。心理的な視点でも「have to」と「want」の混同という注意点が存在します。
集団帰省をやってみたい。
宮崎の学生と話していて、みんな口をそろえて言っていたのが「宮崎に帰っても、県庁か銀行かJAとか新聞社だよね」というものでした。そんな事は無くて、その他にも「いい会社や、魅力的な人」はたくさん存在します。地元にもめっちゃイケてる人がいるのに、学生達は「知らない」。学生たちが「なんとなくのイメージ」で地元を見てしまっていると感じました。
→大人にも当てはまりますね。

それだったら、その人たちに会える場があればいい。できれば地元で開催したい。ただ、人と会える場だけではなく、その地域がもっている雰囲気や力も感じてもらいたいからです。その人の良さって、都内の会議室より、その人が「生きている場所」でこそ伝わるものがあると思うんです。
ただ、学生を地元に呼ぶって交通費かかるから大変です、だったら、「お盆と正月」なら田舎に帰ってるんじゃないか、かつ、東京だけでなく大阪や福岡に行った人も、帰ってこれる!と考えました。
→学生にとっては、選択肢を得て具体化できる機会でもあり、「地元の魅力的な大人」を知る機会にもなる。地方にとっては、地元の企業に優秀な学生が入社してくれる可能性が高まる。そして地方と学生が「理解し合う機会、繋がる機会」になりますね。実施しない理由がない。
⑦ 「今の地元」を知ることができる仕組み へつづく
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
石川智章
「栃木のしゅし」総合統括
県南エリア出身
関連記事
Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!