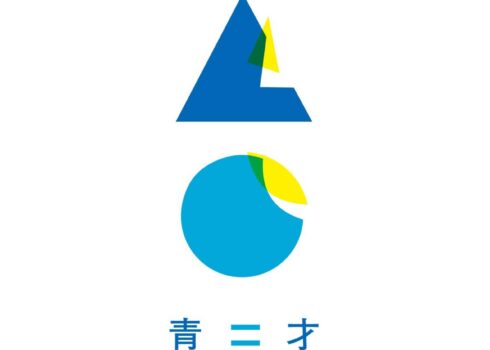- とちぎのしゅし
- 子どもの「食べもの好き嫌い」問題!<後編>|「いつもありがとう!」お母さん通信
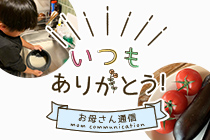
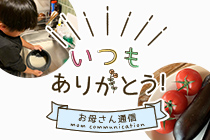
子どもの「食べもの好き嫌い」問題!<後編>|「いつもありがとう!」お母さん通信

みなさんこんちは。前回はお母さんたちに「子どもたちはどんな食べものが嫌いなのか?」「どうやって対処しているのか?」などをヒアリングした結果や、オススメのレシピをご紹介しました。
「ウチも同じだよ〜」と共感できる部分や、好き嫌い克服へとつながる新たなアイデアは見つかりましたか?
今回<後編>では、ウチの子ども達がお世話になっていた幼稚園さんにご協力いただき、ベテランの先生やスクールカウンセラーの先生からアドバイスをおうかがいしてまいりました。
お子さんの「食べもの好き嫌い」に悩んでいるお母さん!この記事を読むと「少し前向きな気持ち」になれると思います!ぜひ最後までご覧くださいね。

「お母さん頑張りすぎないで!」スクールカウンセラーからのアドバイス
スクールカウンセラーをされている先生に「子どもの好き嫌い」に悩む、お母さんたちへのアドバイスをおうががいしました。
お母さんがあまり神経質にならない方がいい。
お母さんが「食べてほしい・食べさせなければ」と思い、頑張って時間もかけて用意したのに食べてくれない。その結果、お母さんは「ガッカリ…こんなに頑張ってるのに、何で?」「つらい、悲しい」その感情が「怒り」になることも。
食べないことに怒ってしまい、落ち込むお母さんもいます。好き嫌いの度合いにもよりますが、お母さん自身あまり神経質にならないで!お母さんは悪くないんです、よくやっていると思います!
ご飯作りは毎日のことで、本当に大変なんですよね。
「うちの子、野菜を食べないんです」と、よく相談を受けますが…。
「先生!うちの子は野菜をぜんぜん食べないんです!」と心配するお母さん。詳しくお話を聞くと「ジャガイモは食べます」とか「ジャガイモしか食べなくて…」とおっしゃいます。
でもこれって、野菜の多くは食べられないけれど、ジャガイモは食べられていますよね。ジャガイモは野菜です!野菜を食べられているってことですね。
なにがなんでもピーマンを食べなくてもいいと思うんです。幼稚園も学校も強要はしません、大丈夫。
今はイヤでもこの先食べるようになるかも。成長とともに食べられるようになる可能性は大です、お母さん焦らずに!
子どもは本能的に、感覚的な反応で食べものへの拒否反応をします。
子どもが「香りが強い」食べもの、「苦みがある」食べものに一歩引くのは本能的な反応なんです。
また、小さいうちは、目からの情報が強いので、料理の「見た目」が大事だったりしますね。
同じ材料だけど調理方法などで見た目が違うと、子どもには「別の食べもの」に見えることもあります。
幼い子は味で「おいしい」と感じれば、材料が何であっても食べてしまうので、調理法や見え方の変化は有効ですよ!
年齢によって発達段階がある。焦らない、急がない!
子どもたちの食べ方は、「手づかみ・スプーン・フォーク・お箸」というふうに順番を追って発達しますよね!
食べものに関する発達も年齢によって違うし、子ども一人一人でも違います。「~しなければならない」を気にしすぎないことが大切です。
お子さんの好き嫌いを心配するのはお母さんとして当然なこと。愛情があるからこそです。
お母さん、急がなくて大丈夫ですよ!

ベテラン先生に聞く!子どもたちの「食べもの好き嫌い」どう対応してる?
続いては、幼稚園のベテラン保育者 である先生に、子どもたちの「食べもの好き嫌い」に、どう対応しているのかをおうかがいしました!
<保育の現場で実際におこなっていること・気をつけていること>
⓵おいしそうに、集団で食べる。
まず保育者が「おいし〜い」と言いながら、おいしそうに食べるようにしています。園での食事に関する強みは、「集団で食べる」ということです。お友達がパクパク食べている姿を見て「私も食べてみようかな」という気持ちになれたりします。
②ほめる
私たちの園では、苦手なものは自分で量を調節できるように、子どもに聞きながら配膳をしています。そして、少しでも食べられたら、「すごいね!」「体が元気になるね!」と、前向きな言葉でほめています。
また、そんな「すごいね!」という言葉を聞いている周りの子も「食べられるって、すごいことなんだ」という気持ちになり、食べられるキッカケになったりすることもありますよ。
③楽しい時間を意識する。
とにかく食事中は「楽しい時間」になるように、テーブルにお花を飾ったり、無地のランチョンマットを敷いて「食事が映えるようにする」などの「環境づくり」も配慮しています。
④無理に食べさせない。
あとは、無理に食べさせないことも大切ですね!
<ご家庭でもできそうな、好き嫌いを克服するアイデア>
⓵親子で「楽しい食事の時間」をもちましょう!
「いただきます」「美味しいね!」「園でお昼に◯◯を食べたよ」「ごちそうさまでした」ゆったり会話しながら、楽しい雰囲気で食事ができるといいですね。食事の時間が楽しいと感じられると、「食」へのモティベーションが上がります!
②幼稚園・保育園・学校と、ご家庭とで「連携」しましょう!
例えば「おうちでピーマン食べられたんだってね。お母さんから聞いたよ〜すごいね!」と声かけし、多くの大人に認められるなど「成功体験」を積んでいくことで、自信につなげていきます。
先生とお母さんとでタッグを組んでみましょう!
③食事の準備を一緒にしてみましょう!
子どもに役割を与えて、食事の準備を手伝うことで、「食」に対して「ポジティブな気持ち」になるキッカケを作ることができます。
できることからチャレンジ!

まとめ
2回にわたり、子どもの「食べもの好き嫌い」問題についてお伝えしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
自分が子どもの頃を思い出してみると、食べられないものが色々とありました。今となっては気にせず食べていたり、むしろ好んで食べている食材もあります。成長とともに「味覚」も変化していくんですね。
今回、先生方へのインタビューで分かったのは、私たちは「子どものために!」と必死になる前に、「子どもと一緒に食を楽しむ」ことを意識したほうが良いということ。
お母さんたち、頑張りすぎていませんか?
お母さん自身が楽しい気分でいることが大切なんですね。
お仕事をされている場合、平日は慌ただしく過ごされているかと思います。お休みの日など、ご自身に余裕のある時に、お子さんと一緒にご飯の準備をしてみたり、テーブルに花を飾りいつもの食事とは違う雰囲気にしてみるのはいかがでしょうか?
私も週末、子どもと一緒にメニューを考えて、夕飯づくりしてみようと思います。では、次回もお母さんたちが元気になれたり、役に立つような情報をお届けいたします。
どうぞ、お楽しみに!
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
yukie
編集・ライティング担当
県南エリア在住
関連記事
Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!