- とちぎのしゅし
- 「子どものとなり佐野」子ども・子育て家庭を支援|とちぎのSocialGood
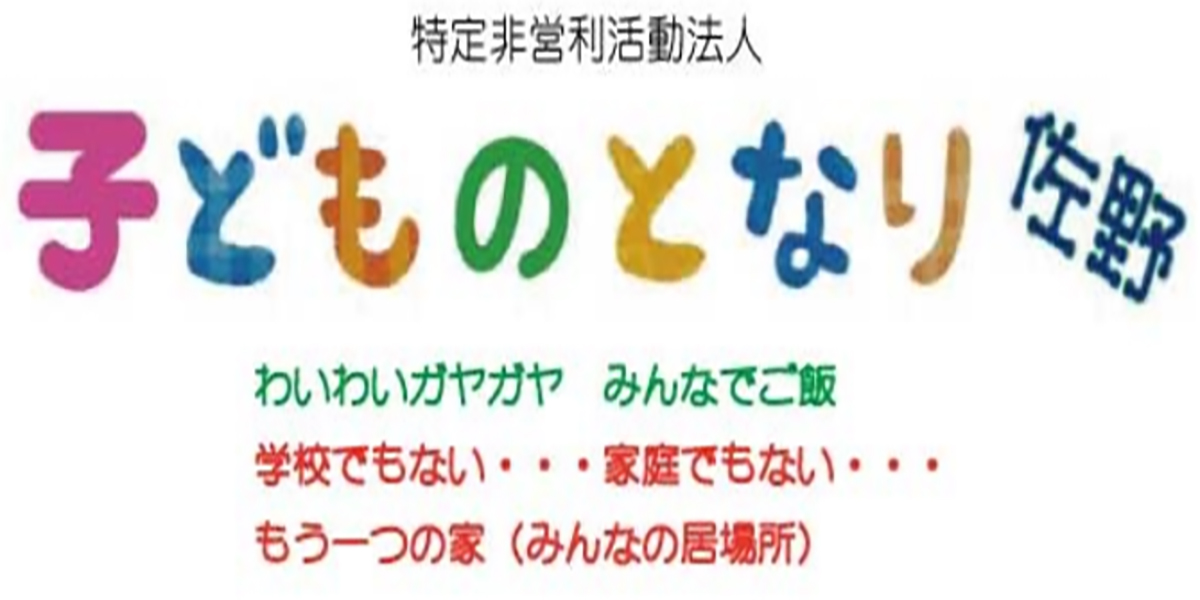
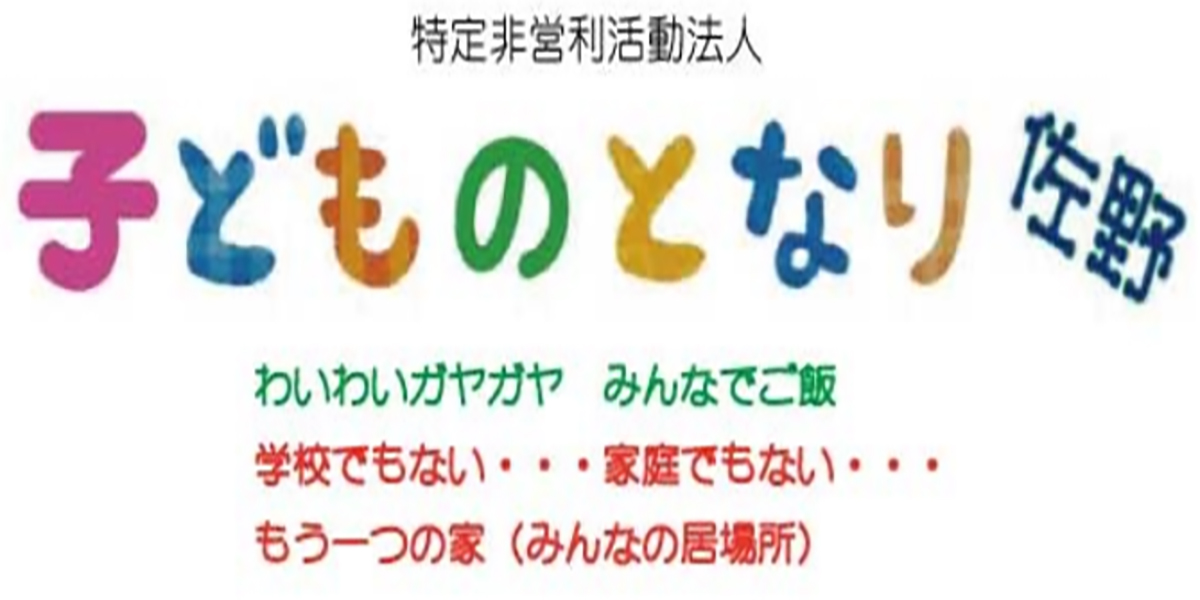
「子どものとなり佐野」子ども・子育て家庭を支援|とちぎのSocialGood

今回は佐野市で、子ども・子育て家庭の支援を行う「NPO法人子どものとなり佐野」をご紹介します。
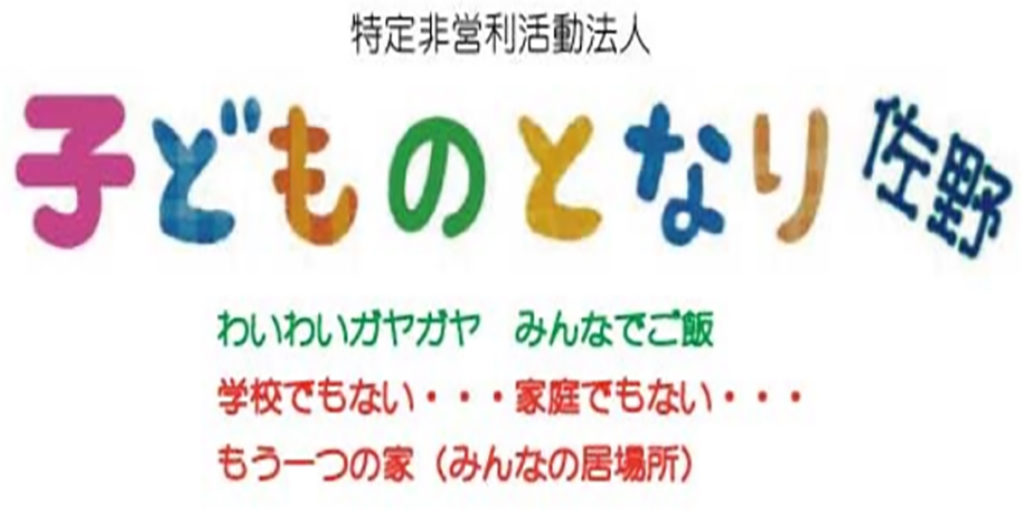
副理事長の熊倉さん
「子どものとなり佐野」の副理事長、熊倉 百合子(くまくら・ゆりこ)と申します!

私は(独法)国際協力機構 JICA栃木デスクで、「青年海外協力隊」の活動希望者の相談を受ける他、JICAプログラムを紹介するなど、栃木県の窓口として「地域と人をつなぐコーディネート」を本業としています。
その本業とは別に「子どもと関わる仕事をしたい!」という想いから、地元の佐野で「子どものとなり佐野」の活動にも携わっています。
これからご紹介する「子どものとなり佐野」は、2019年に設立されたNPO法人で、ボランティアの方々に支えられながら子どもの支援を実施しています。
まずは活動の柱となっている、食事支援、子どもの居場所づくり、学習支援、親子支援についてご紹介したいと思います。
活動内容
・食事支援(子ども食堂)
食事支援として週に1回、お弁当を30食ほど配っています。庭の畑で採れた野菜や寄付していただいたものをお弁当の食材として活用し、ボランティアの人たちが調理を担当。完成した手作りのお弁当は、活動拠点「犬伏(いぬぶし)の家」で渡すこともあれば、ご家庭に届けることもあります。

従来は「子ども食堂」を実施していましたが、コロナ禍となり継続が難しくなりました…。
食事支援をどのような形で継続するか悩んだ末、思い切ってお弁当の配布に切り替え、食事の提供を続けています。
お弁当を渡すときには生活に必要な食材も一緒に渡します。それらの食材は家庭で食べきれない食べ物を持ち寄り集めて寄付するという「フードドライブ」という活動を通して集めています。
フードドライブの活動は、「犬伏の家」に持ち寄ってもらったり、道の駅やショッピングモールにブースを出展して集めることもあれば、他団体が定期的に集めて持ってきてくれることもあります。子どもたちの長期休みになる春・夏・年末には、「食材配布会」として、これらを必要な家庭にお渡ししています。
・子どもの居場所/学習支援
私たちが関わる子どもたちの中には人に大切にされる経験が乏しく、自己肯定感の低い子もいます。そういった子どもたちが、遊びや勉強などの生活支援を通して「自尊感情を回復・獲得」できるような場を提供する役割も担っています。

週に1回実施している子どもの居場所づくりでは、夕方頃に活動拠点へ送迎後、子どもたちはお風呂に入ったり、勉強したり、遊んだりして過ごし、夜には自宅に帰るといった流れで過ごしています。
また、学習支援も週に1回の頻度で実施し、スタッフとマンツーマンで勉強をする場を用意しています。学習塾や学校に通うことが難しい状況にある子どもたちを対象に、日常的な学習を行えるよう取り組んでいます。
・親子支援
少し前の日本では、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に暮らす家庭が大半でしたが、今は親と子どもだけで暮らす家庭も少なくありません。
そういった状況もあって、子どもの支援活動をやればやるほど「親も大変」であることに気づかされてきました。子どもだけではなく親御さんのフォローも必要なんですよね。
子育てに対する負担や不安や孤立感を和らげることを通じて、親御さんが自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整えるための支援も行っています。
活動への想い
・野外キャンプを経験して見つけた人生の軸
「子どもと関わる仕事をしたい」という想いは、大学進学時からありました。当時から子どもたちの「自己肯定感を高める活動」に興味があり、どんなことができるのか模索していました。そんな時に出会ったのが、子どもたちのための野外活動の場…キャンプです。
活動している埼玉県の「ひげっちキャンプ場」は、子どもたちのために作られた専用キャンプ場。キャンプ生活で仲間とのやり取りを通して、お互いを尊重し、またそれぞれの長所を伸ばせる環境の中、子どもたちは自由に自分たちの暮らしを作り上げます。自分を好きでいることをとても大事にしていて、私自身も自己肯定感が高まり、すごくプラス思考になりました。

そこからキャンプ活動に関わり続け、現在では子どもたちと直接関わる学生リーダーをコーディネートする立場になりました。自分の活動で子どもたちが喜んでくれるのがすごく嬉しいですし、自己肯定感を高めることを意識した行動は、「子どものとなり佐野」の活動とも共通しています。
キャンプの世界を経験したことで、私の人生の軸が定まったのだと思います。
・青年海外協力隊の活動を終えて日本の地域課題を見つめ直す

野外体験、自然学校みたいなことをやりたいと思って帰ってきましたが、日本でも子どもの貧困が地域課題としてクローズアップされはじめていた時期に帰国し、「海外だけじゃないぞ!」と感じました。この身近な課題を自分が解決しなきゃと思ったんです。
活動テーマの中心には「子ども」というキーワードがずっとありましたが、「どういう子に何をしたいのか」が協力隊の前後で変わったんですね。自分の中でも明確になった気がして腑におちる感覚がありました。海外へ行き国外の課題と向き合ってきたからこそ、日本の地域課題が「自分ごと」になったのだと思います。
・地元の佐野市で活動に関わる
大学進学時は東京に出ていましたし、栃木県内で暮らしていない期間もありましたが、最終的には佐野に戻って活動したいという想いがありました。自分の生まれたところで他の人たちの役に立てたらいいなぁと思っていたんです。
今の団体のような子ども支援を行っている地元団体を探してみたのですが、県内にはあっても佐野市には無く、自らNPOの設立を考えるようになったんです。とはいえ、佐野で何かを始めるにも、一緒に活動する仲間が集まっていない状況でした。
そんな状況が続いたある日、JICA栃木デスクで働いていた縁から、今の理事長がNPO法人を佐野で立ち上げることを知り、共に活動することになりました。
今後の展望
活動の拠点となる場所を借りていますが、週に2日ほどしか活動できていない状況です。
やはり目指したいのは、支援を必要とする人が必要な時にアクセスできる時間と場所を提供することだと思っているので、いかに活動回数を増やしたり、関わる人たちを増やしていくかが課題となっています。
関わる人を増やすためには、団体の活動内容を正しく知ってもらい、良き理解者を増やすことと、「若者の人材育成」が必要だと思っています。また、フードドライブをはじめとする団体の活動を通して、若い人たちと一緒に活動していくことの意義も感じています。
ここに集うみんなが「楽しかった!良かった!」と思えるような場づくりを今後も続けていきたいと思っています。

中学生、高校生のうちからハードルを上げずに活動に参加できるような環境と経験があれば、大人になっても自分のライフステージに合わせて、色々な関わり方ができると思うんです。ですから佐野市で若者の人材育成を実施できたらと考えてます。

「栃木で挑戦しようとしている人に一言、お願いします!」
楽しいと思ったことを周りに波及させることで、いつかは「誰かの役に立つ」と思います。自分を信じてやりたいことに挑戦してみてください。
そして栃木県で挑戦していただけることは、私たちが一緒に暮らす「子どもたちのため」にもなると思うので、やっていただきたいと思います。
参加・寄付の情報
正会員・賛助会員・ボランティア会員を募集しています。
詳細については下記のページよりご確認ください。
https://kodomonotonari-sano.jimdofree.com/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E5%8B%9F%E9%9B%86/
団体の基本情報
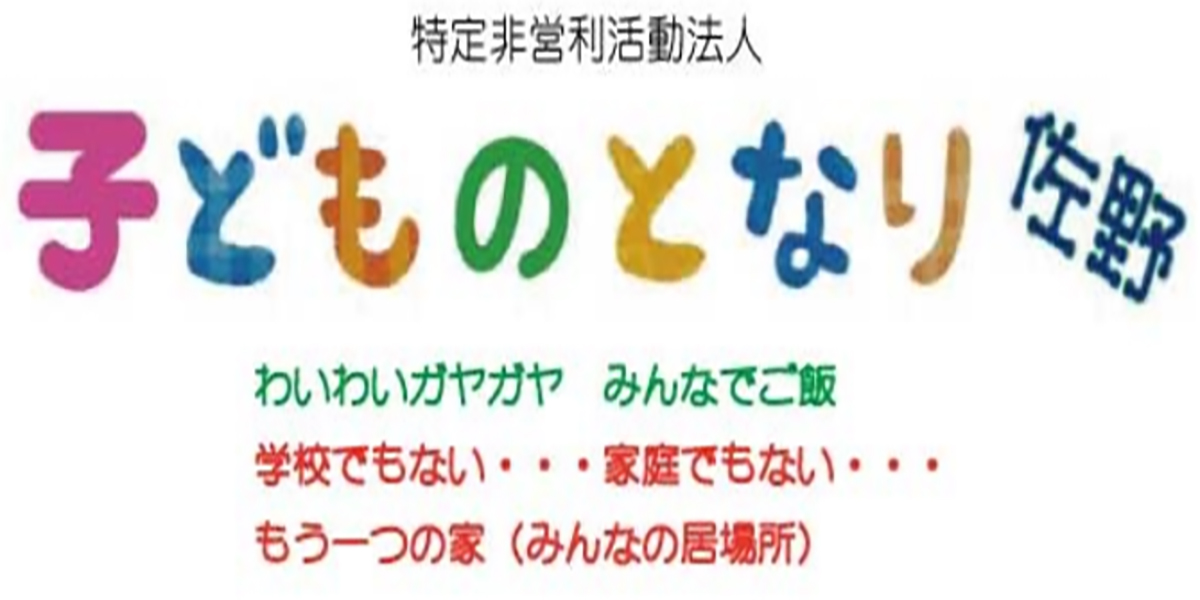
| 団体名 | 子どものとなり佐野 |
| 活動ジャンル・テーマ | 子ども・子育て家庭の支援 |
| 活動エリア | 佐野市 |
| NPO設立年 | 2019年 |
| スタッフの数 | なし |
| 住所 | 栃木県佐野市犬伏新町2070-1(活動拠点) |
| メールアドレス | kodomonotonari.sano@gmail.com |
| 団体SNS | フェイスブック |
| 団体HP | https://kodomonotonari-sano.jimdofree.com/ |
編集部コメント
子育て家庭の支援は、地域で暮らす人たちに必要な取組みの一つだと思います。
食事の支援でいうと、食べきれなくて食材を捨ててしまう人もいれば、お金を払って食材を買っている人もいるんですよね。その他のサービスについてもそうですが、支援を必要とする人のもとに必要なものがいき届くように、地域でぐるぐると上手く循環していくといいなと思います。
多くの人にこの記事が読まれますように!
そして、地域で良い活動がもっと増えることを願います。
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
藤本尚彦
リサーチ・ライティング担当
県南エリア在住
関連記事Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!
















