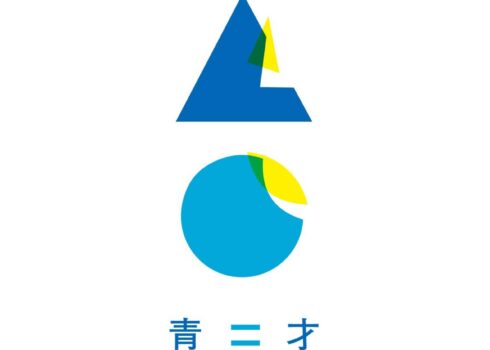- とちぎのしゅし
- 渡辺敬晴(なかがわ水遊園・飼育統括)|tochigi gene vol 4


渡辺敬晴(なかがわ水遊園・飼育統括)|t...
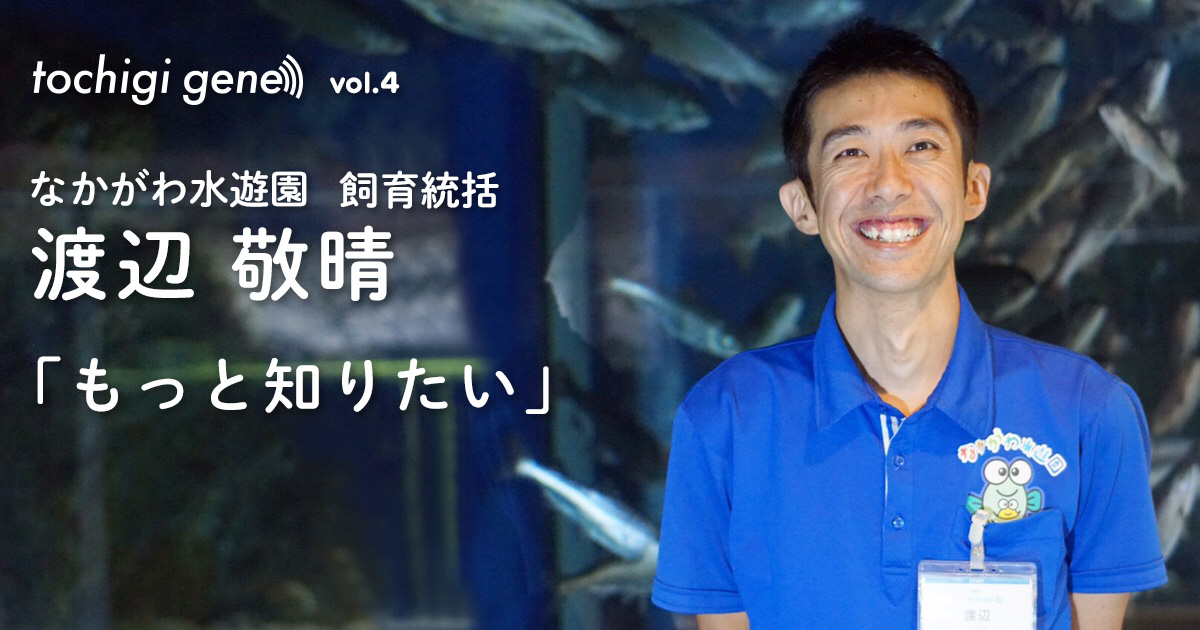
渡辺敬晴 (わたなべ よしはる)
なかがわ水遊園 飼育統括(学芸員)
県央エリア 栃木県大田原市在住
2001年に日本でも数少ない「淡水魚メインの水族館」として栃木県大田原市に誕生した「なかがわ水遊園」
コンセプトは「那珂川から世界の川に」。施設内の魚の展示も地元那珂川の上流から下流、そしてアマゾン川という構成で展開されている魅力的な水族館です。年間来場者数も2016年に28.5万人と大人気!
そんな「なかがわ水族館」で生き物たちの「飼育総括」を担っているのが渡辺さん。仲間から博士と言われるほど「淡水魚の知識」をお持ちでいらっしゃる渡辺さんに「飼育のポイント」や「発想」をおうかがいしました。
もくじ
「何か、変だな」
なかがわ水遊園ではどの様なお仕事をされているのですか?
私は、なかがわ水遊園の生き物の飼育を統括しています。その他にも、展示の仕方を考えたり、メンバーの教育、お客様への解説など、総合的にマネジメントしています。

魚を飼育する上で大切な事は何でしょうか?
魚はしゃべらないので、こちら側がいかに「気が付つけるか」という点です。専門的な知識ももちろん必要なのですが、直感的な部分はもっと大切。日々のちょっとした変化を感じ取ることが重要です。
例えば、自分の「子供」や「ペット」を毎日見ているとちょっとした異変に気づきやすいですよね。「何か、変だな」って。
「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、水族館の場合は逆で、「森を見て木を見ず」。その方が「何か」を見つけやすいと思います。病気も一匹から全体へ一気に広がる事もあるので。
→なるほど。全体を見る中で個の異変をキャッチする訳ですね。そこから専門知識をもって対処する。その上では最初の「気づく事」が大切であると。

具体的に、チェックするポイントはあるのでしょうか?
色々あります。「餌の食べ方」「泳ぎ方」「病気」など。あとは「季節ごとの対応」「繁殖期の対応」も大切です。
天然記念物となる生き物は、繁殖させる事もミッションに入るので、細心の注意を払います。「水温」「水流」「光の明るさやその時間」などの環境面を配慮。魚はこういった所を感じて繁殖期を迎えたりするので、それぞれの魚の生態や特徴をいかに理解しているかが大切です。
面白い話で言えば、魚は成長していくと「喧嘩」もします。なので、魚同士の相性を見たりもしますね。
→えー!魚にも個性があるんですね。
はい、魚それぞれで違いがあります。魚が小さい時は解りづらいのですが、大きくなると個性も出てきます。よく泳ぐか、よく食べるか、攻撃性があるか、など同じ種類の魚でも微妙に違うんです。
→魚を健康に飼育するためには、ケンカさせない事、そして、繁殖させる事など、様々な視点があるんですね。

リスクはどんな事でしょうか?
最大のリスクは魚が死んでしまう事。過去に水槽の魚まるまる50匹が全滅してしまった事があります。原因は機械の故障でした。
水族館には、色々な所から魚がやって来ます。業者から購入したり、川から採集したり。その中で、魚達が水族館にやって来た時が一番体調を崩しやすいので、メンバーは神経を使います。
とはいえ、魚も生き物、いつかは死んでしまう。なかがわ水遊園には魚が約2万匹いるので、毎日なにかしらの魚が死んでいるのも事実です。
2 「もっと知りたい」「全部知りたい」 へ つづく
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
石川智章
「栃木のしゅし」総合統括
県南エリア出身
関連記事
Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!