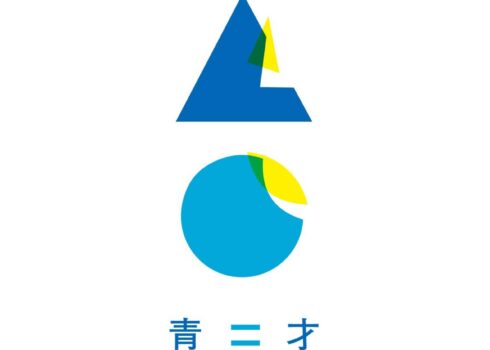- とちぎのしゅし
- 増田真樹(Techwave:編集長)|tochigi gene
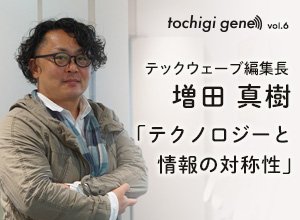
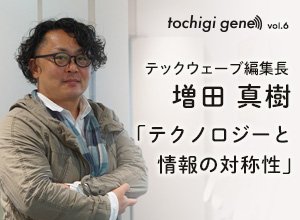
増田真樹(Techwave:編集長)|tochigi gene

増田真樹(ますだまさき)
Techwave(テックウェーブ)編集長
県央エリア 宇都宮市在住
栃木県宇都宮市に住みながら、日本を軸としたテクノロジー経済WEBメディア「テックウェーブ」を運営する増田真樹さん(通称:マスキンさん)。
人と人を繋ぐ(ネットワークをつくる)のがメディアという考えの元、WEB媒体だけでなくリアルのイベントも開催。プログラマー経験やアメリカでの就業経験を活かし、今までに国内外50社以上のスタートアップをサポートした実績をお持ちです。
地方(栃木)に拠点をおきながら東京や世界を行き来し、「最新のテクノロジー」を紹介しているマスキンさんに、そのお話をうかがいます。
- ページ構成 -
①テックウェーブについて
②7歳からプログラミングをはじめた幼少期
③キャリアストーリー:アメリカ時代とスタートアップ支援を経てWEBメディア運営へ
④イベントを通じて地域に問う
⑤キャリアデザインに関するアドバイス
①テックウェーブについて
テックウェーブというメディアについて教えてください。
テックウェーブは、日本を軸に「社会を変える可能性があるデジタルテクノロジー」を紹介するメディアです。デジタルトランスフォーメンション(ITプロダクトを導入する事で起こる変革)は、企業においても重要。企画や意思決定者の方達にも情報ニーズがあると捉えています。
また、海外のテクノロジ―企業との接点も大切にしており、海外のテクノロジーを日本に紹介したり、逆に日本のテクノロジーを海外に繋げる動きもしています。
メディアを運営する上で、大切にされている事はありますか?
読者や取材対象にとって「役に立つ」情報や機会を創出する
ユーザーにとって「役に立つ情報」である事を大切にしています。煽ってPVを稼ぐだけで中身の無い情報は作りたくない。「使える情報」という点では、その「サービス」しかり「裏側にいる本当のキーマン」も紹介し、結果的に読者と取材された側が「繋がれる仕組み」を作りたいと思っています。国内・世界にいるユーザー間の距離を縮めたいですね。

情報の非対称性をできるだけ無くす
現在、世界各国で「交流」は実現されていますが、「情報」という点では「ひとつのキーワード」でも場所によって差があり、結果的に「解釈」もズレている様に感じています。
例えば「電気自動車」や「宇宙事業」を展開する世界的な起業家イーロン・マスク氏でいえば、日本にはシリコンバレーでの動向ばかり入ってきますが、中国の都市と連携をしていたりもする。グローバル目線でみればもっと別の見え方が生まれてきます。
世界の主要な都市を俯瞰的に見て「ひとつのキーワード」を把握した方がいい。それを助ける「情報メディア」や「人的交流を促す仕組み」が必要だと考えているんです。
「情報や解釈の誤差」を出来る限りなくす為に、世界各地の「拠点」から情報を整え、各国の「ユーザーとの交流」を実現していきたい。起こっている事実の認知化を促しつつ、「情報の非対称性」を無くすイメージで、しっかり情報を吸い上げたいですね。

→日本や地方の一か所にいる場合、情報でしか世界の事は理解できないですよね。その情報の正確性が高い事はありがたいことです。受け手としては情報の捉え方や扱い方には気を付けたいですね。
現在の形になるまでのキャリアを教えてください。
もともとは「プログラマー」でした。7歳の頃から簡単なゲームをつくってましたよ。 家は音楽一家。私は絵画にも興味を示していたので、一人マルチメディアみたいな感じだったな。笑
18歳くらいから、テクノロジーに関連する「執筆」もする様になり、後にアメリカと日本を行き来する生活になりました。最終的にはEUの世界的企業に勤務したり、個人として海外の企業と関係を持つ中で、国内外50社以上のスタートップの立ち上げに携わりました。
先ほど話した通り、7歳からプログラミンをやってきたので「つくってなんぼ」という姿勢が今もベースにあります。子供の頃から「ITの可能性」を強く感じており「広めて普及させる」ことを一貫してやってきています。
→7歳!!当時の日本で、そんな事がありえたんですね。
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
石川智章
「栃木のしゅし」総合統括
県南エリア出身
関連記事
Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!