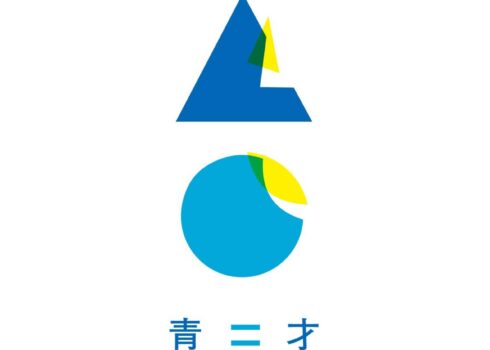- とちぎのしゅし
- 池上知恵子(ココ・ファーム・ワイナリー専務)|tochigi gene vol 3


池上知恵子(ココ・ファーム・ワイナリー専務)|tochigi gene vol 3

池上知恵子 (いけがみ ちえこ)
ココ・ファーム・ワイナリー 専務取締役
県南エリア 栃木県足利市出身
こころみ学園とココ・ファーム・ワイナリーの創立者である川田昇氏のご長女であり、現在の専務取締役である池上さん。障害をお持ちの園生が活躍できる場をつくりつつ、国や企業、飲食店や専門家など多方面で評価されるワインを造られています。
東京の出版社で勤務した後、地元の足利市に戻ったUターン経験者。大変な事もたくさんあるであろう、その活動と、それを支える想いや考えをうかがってきました。
もくじ
1、ワイン造るよー!
2、こころみ学園とココ・ファーム・ワイナリー
3、園生に教えてもらうもの
4、父から引き継いだもの
5、未来のしゅし
1、ワイン造るよー!
◆どんな想いで、編集者を辞めて足利に帰ってこられたのですか?
「想い」というのはなくて「なりゆき」だったような気がします。昔からあんまり深く考えないで、行き当たりばったりでやってきました。「お前の性格は水だ」と言われた事があります。器によっていくらでも変わるみたいです(笑)。
私の父の実家は果樹園、母の実家は酒屋でしたから、ワイン造りは宿命だったのかもしれません。生まれた時点では本人の「想い」はないですよね(笑)。「ワイン造るよ!」って言われて「じゃあ大学いくよ!」って感じでした。

◆東京ではどんな生活をされていたのですか?
栃木県の足利市に生まれ育って、東京女子大に入学して社会学を専攻。※入試があった1969年は東大の入学試験が無かった年だったの(笑)。
その後、出版社で編集の仕事をやっていました。当時の勤務先は神宮前4丁目、今の表参道ヒルズの近くにあって、あの頃はセントラルアパートも元気で、今思うと面白い時代でしたよ。
出版社勤務の頃に子どもが生まれました。何が大変って8時間続けて寝られないのが一番大変だった。育児は朝9時から夕方6時までで週40時間の所定労働という訳にはいかないものね。
◆ワイン造りにむけ再度、大学に通う。
その頃、父からワインを造るという話があり、「学生になれば自由な時間があって8時間続けて寝られるのではないか」というふらちな理由でもう一度大学に行き醸造を学ぶことにしました。東京農業大学を受験して入学したのですが、これが行ってみたら、実験やら実習で大忙し。
一度目の大学の時は「大学闘争」で授業が行われない休講が多く、自由な時間がたくさんあったけど、二度目の大学生活は、勉強することがたくさん。いろんな人にお世話になって、子育てをしながら大学に通いました。1984年、卒業と同時に足利に帰ってワインづくりをはじめました。
今考えてみると、田舎でワインをつくるという選択は「子どもを育てる」という生活を経験していたからできたのかもしれません。人や自然に寄り添って働く仕事は、定時の労働契約で働くビジネスとそぐわないところがありますからね。
→特に想いというものは無かったのですね!それでも、結果として再度大学に通われ醸造を学び、その後、足利でワイナリーを運営されている。その一連の行動は凄い事だと思います。
2、こころみ学園とココ・ファーム・ワイナリー へ つづく
\SNSで記事をシェア/
この記事を書いた人
石川智章
「栃木のしゅし」総合統括
県南エリア出身
関連記事
Related
この記事を読まれている方にはこちらもおすすめ!